*
会社の2階にある小部屋に呼び出されたのは、去年の5月だった。神妙な顔で、スチールのイスに座った社長は、僕に向かって、おもむろに会社の経営状態を語りはじめた。
赤字だ、時代だ、売上の減少だ─。
いろいろ喋っていたが、それは僕の耳を、右から左へと通過していった。業界全体が不況であることは10年前から分かっていたことであり、なにを今更という話だった。
ところが、最後の言葉に耳を疑った。
「─そうゆうことで、ボーナスが払えなくなったからね」
え…、いや、待て。それはこの状況を放置してきた、お前ら経営陣の責任だろ…。まずは、お主が腹を召すのが、スジってモンじゃないのか。
その瞬間、僕はすべてを悟った。
つまり社長は、経営者としてのモラルをかなぐり捨て、従業員のボーナスをカットすることにより、自らの保身に走ったのである。
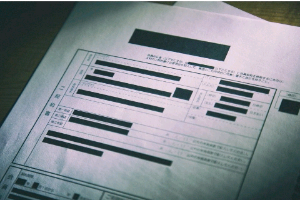
クロとボーナス
そして、ボーナスの無い日々は、僕の心を着実に蝕んでいった。仕事でトラブルがあれば、以前なら厄介だと思いつつも、小手先で対応していたことも「ボーナス無い僕がそこまでする必要ないめう」という思いが頭をよぎり、何もしなくなった。
絶えず襲い来るボーナスカットの焦燥感。
僕は、当たり前にあった日常が、ある日突然、失われる無力感に、クロのことを思い出していた。
小学校のころ、僕のうちでは「クロ」という名の仔犬を飼っていた。姉が学校の帰り道に拾ってきて、その日からクロは我が家の一員になった。
日中は放し飼いにしていたため、ときおり隣家の庭先に忍び込み、干してあったベットカバーを引き破るなどしていたが、ふだんはとても人懐っこい、きわめて愛くるしい仔犬だった。
そのクロが、ある日とつぜん倒れた。犬小屋の中に力なく横たわり、僕が「クロ…クロ…」と呼びかけても、キューンと、ノドを細く鳴らすだけだった。もふもふしていた黒毛は枯れ果て、顔を地面につけて、口のはしから涎が垂れている。
僕はクロの背中をなでながら、ひょっとして、誰かに毒を盛られたんじゃないかと訝った。
そして翌日、クロは静かに息を引き取った。まだ生後、1年足らずの理不尽な最後だった。これから僕とともに歩むはずだった未来は、無残に断ち切られたのである。
終わらないリベンジ
クロとボーナス。それは、当たり前にあると思っていた日常が、ある日とつぜん失われるということだ。その喪失感を、ボーナスカットという悲劇により、僕はふたたび味わった。
求人したときには、年2回の賞与ありと、明記していたにも関わらず。その情報は、求職者の重要な判断材料になっていたにも関わらず、それを履行しなかった会社を、僕は絶対にゆるさない。
首を洗って待っていろ。
僕は、激しい憎悪の念を笑顔のうらに隠し、膨大な負の感情を、その体内で熟成させている。ドス黒く変色した感情は、ポコポコと泡立ちながら、腐臭を放ち、ゆっくりと発酵を続けている。
しかし、僕になにができるのだろう。
この理不尽な仕打ちに、どうやってリベンジできるのだろう。ボーナスを失った僕は、クロを失った、あのときと同じように、どうしようもない無力感に苛まれている。